■Staff grief and support system for Japanese health care professionals working in palliative care
モナシュ大学看護学科講師
下稲葉 かおり
| はじめに |
 この研究を開始する背景には、本研究の研究者(下稲葉)の医療者としての経験と、日本の医療者から寄せられたさまざまな声がある。 この研究を開始する背景には、本研究の研究者(下稲葉)の医療者としての経験と、日本の医療者から寄せられたさまざまな声がある。
 約10年前にオーストラリア緩和ケア研修に参加した際、初めて「スタッフのケア」という講義を緩和ケア病棟師長から受けた。また、オーストラリアで看護師の資格取得後、緩和ケア病棟で勤務する中で、Debriefing session(医療者のための振り返りセッション)に参加する機会があった。これはスタッフの抱える問題や感情に焦点が当てられており、スタッフのケアの1つであった。これらの経験から、「医療者もケアされる対象であること」「医療者である私たちがもつ感情もOKである」との気づきがあった。 約10年前にオーストラリア緩和ケア研修に参加した際、初めて「スタッフのケア」という講義を緩和ケア病棟師長から受けた。また、オーストラリアで看護師の資格取得後、緩和ケア病棟で勤務する中で、Debriefing session(医療者のための振り返りセッション)に参加する機会があった。これはスタッフの抱える問題や感情に焦点が当てられており、スタッフのケアの1つであった。これらの経験から、「医療者もケアされる対象であること」「医療者である私たちがもつ感情もOKである」との気づきがあった。
 さらに、過去5年ほど日本の緩和ケア病棟にかかわる機会を得ている。その中での私の役割はスタッフのケアと教育である。希望するナースと約1時間ほどの時間をとり、自由に話をしてもらっている。この中でナースたちは、ケアに対することではなく、自らのことを語る。多くのナースが、悩み、疲れていることが伝わってくる。と同時に、「聞いてもらえてスッキリした」「元気がでてきた」という感想もきかれる。ナースも痛み、悩んでいる。その痛みを十分に理解し、サポートを継続して提供していくことの大切さを感じる。そして、2003年から日本において「グリーフケアワークショップ」をオーストラリアのグリーフケア教育者と協力して開催している。このワークショップでは、グリーフケアに関する理論やケアの実際について取り扱うが、全体の半分を占めているのは“グリーフケアに携わる医療者自身のケアについて”である。参加された医療者の方々から、「患者・家族のケアのため…と思って来たが、まずは自分自身が癒されなくてはと気づいた」「良いケアを提供するために、自分をケアしていきたい」というような感想が多いことに気づく。医療者自身も、人生の過程のどこかで悲嘆を経験しながら生きており、他人の痛みに触れることで自分の痛みをさらに経験したり、思い出したりしてつらくなることがある。多くの医療者がこのようなことを十分に考える時間を持たないまま、ケアを続行しているのが現状である。 さらに、過去5年ほど日本の緩和ケア病棟にかかわる機会を得ている。その中での私の役割はスタッフのケアと教育である。希望するナースと約1時間ほどの時間をとり、自由に話をしてもらっている。この中でナースたちは、ケアに対することではなく、自らのことを語る。多くのナースが、悩み、疲れていることが伝わってくる。と同時に、「聞いてもらえてスッキリした」「元気がでてきた」という感想もきかれる。ナースも痛み、悩んでいる。その痛みを十分に理解し、サポートを継続して提供していくことの大切さを感じる。そして、2003年から日本において「グリーフケアワークショップ」をオーストラリアのグリーフケア教育者と協力して開催している。このワークショップでは、グリーフケアに関する理論やケアの実際について取り扱うが、全体の半分を占めているのは“グリーフケアに携わる医療者自身のケアについて”である。参加された医療者の方々から、「患者・家族のケアのため…と思って来たが、まずは自分自身が癒されなくてはと気づいた」「良いケアを提供するために、自分をケアしていきたい」というような感想が多いことに気づく。医療者自身も、人生の過程のどこかで悲嘆を経験しながら生きており、他人の痛みに触れることで自分の痛みをさらに経験したり、思い出したりしてつらくなることがある。多くの医療者がこのようなことを十分に考える時間を持たないまま、ケアを続行しているのが現状である。
 上記のような研究者の経験と現場の医療者の抱えている課題が、今回の研究の強い動機づけとなった。 上記のような研究者の経験と現場の医療者の抱えている課題が、今回の研究の強い動機づけとなった。 |
 |
I 研究目的 研究目的 |
 日本の緩和ケアの現場において、遺族へのグリーフケアの必要性が年々注目されるようになっている。緩和ケア病棟では、それぞれに遺族へのグリーフケアの提供が試みられている。これに合わせて、亡くなりゆく人々をケアする医療者のグリーフも徐々に注目されるようになってきた。なぜならば、患者を看取るという喪失体験のみならず、他者に「グリーフケア」を提供するにあたって、ケア提供者は自らの悲嘆と向き合うことになるからである(Kaplan, 2000)。悲嘆によっておこる反応は、ストレスによっておこる反応と似ており、悲嘆そのものもストレスの原因となるといわれている。これらの結果として、緩和ケアの現場で働く医療者に適切なサポートが必要であることは明らかである。しかし、「医療者の経験する悲嘆」について十分に考察されてきたとは言いがたく、「医療者の悲嘆へのサポートシステム」について確立されているとは言いがたい。本研究の中では、日本の緩和ケアにおけるナースのグリーフの特徴を明確にし、ナースへのサポートを提案することを目的とする。 日本の緩和ケアの現場において、遺族へのグリーフケアの必要性が年々注目されるようになっている。緩和ケア病棟では、それぞれに遺族へのグリーフケアの提供が試みられている。これに合わせて、亡くなりゆく人々をケアする医療者のグリーフも徐々に注目されるようになってきた。なぜならば、患者を看取るという喪失体験のみならず、他者に「グリーフケア」を提供するにあたって、ケア提供者は自らの悲嘆と向き合うことになるからである(Kaplan, 2000)。悲嘆によっておこる反応は、ストレスによっておこる反応と似ており、悲嘆そのものもストレスの原因となるといわれている。これらの結果として、緩和ケアの現場で働く医療者に適切なサポートが必要であることは明らかである。しかし、「医療者の経験する悲嘆」について十分に考察されてきたとは言いがたく、「医療者の悲嘆へのサポートシステム」について確立されているとは言いがたい。本研究の中では、日本の緩和ケアにおけるナースのグリーフの特徴を明確にし、ナースへのサポートを提案することを目的とする。
 本研究では、下記の4点に焦点をあてている。 本研究では、下記の4点に焦点をあてている。
 1)仕事に関連したナースの悲嘆の認識について 1)仕事に関連したナースの悲嘆の認識について
 2)ナースの悲嘆の原因とその影響について 2)ナースの悲嘆の原因とその影響について
 3)日本において現在提供されているスタッフサポートについて 3)日本において現在提供されているスタッフサポートについて
 4)スタッフサポートに関する提案 4)スタッフサポートに関する提案 |
 |
II 研究方法 研究方法 |
 研究対象:日本の緩和ケア病棟で勤務するナースと病棟師長。 方法:本研究は質的研究と量的研究の混合を予定しており、現在、研究方法の最終決定段階である。計画段階では、まず質問用紙を用いてナースの悲嘆を測定後、同意が得られたナース10名ほどからインタビューを実施し内容を深める予定であった、しかし、それらの質問用紙は遺族対象に開発されており、使用が不適切である可能性が高いことがわかってきた。 研究対象:日本の緩和ケア病棟で勤務するナースと病棟師長。 方法:本研究は質的研究と量的研究の混合を予定しており、現在、研究方法の最終決定段階である。計画段階では、まず質問用紙を用いてナースの悲嘆を測定後、同意が得られたナース10名ほどからインタビューを実施し内容を深める予定であった、しかし、それらの質問用紙は遺族対象に開発されており、使用が不適切である可能性が高いことがわかってきた。
 現段階では、2段階にわけた調査方法を検討している。 現段階では、2段階にわけた調査方法を検討している。
- 小児医療に携わる医療者の悲嘆に関して、数々の研究をしているギリシャのPapadatou教授の先行研究を参考に、インタビューを構成する予定である。Papadatou教授には直接連絡をとり、教授の用いた方法を本研究にも用いることに関して快く承諾いただいた。Papadatou教授の研究で行われたインタビューは、主に3つのテーマに沿って構成されている。3つのテーマの1つ目は、「この分野で働くモチベーション」(例として、個人的な疾患や死別などの経験、または意思決定をするにあたって影響を与える因子など)。2つ目のテーマは、「チャレンジと反応」(例として、ストレス因子となるもの、または逆に報いとなっているもの、死ということに対しての個人のコーピングなど)。3つ目は「仕事に関連した満足度」(例として、この分野で働き続けようという思いをもたらす因子、またはこの分野を離れようと思わせる因子、仕事に対する満足感など)である。現在、この3つのテーマに沿って構成されたインタビュー項目詳細をギリシャから送っていただいている。その詳細を見せていただき、小児ではなく大人の緩和ケアに携わるナース、そして日本でケアを提供するナースにふさわしい質問構成であるかを考慮し、本研究のためのインタビューを構成していく。インタビューはプライバシーの守られる個室で、約60-90分を予定している。インタビュー内容の質的研究分析方法は、現在、研究指導者たちと検討中であり、グラウンデッドセオリーやナラティブアナライシスなどを検討している。
- 日本全国の各緩和ケア病棟師長に質問用紙記入を依頼する。質問用紙は、書き込み形式で、病棟におけるスタッフサポートの現状、スタッフサポートに関する今後の展望、スタッフサポートにおける師長の役割、スタッフサポートを展開することにおける難しさなどを聞く予定である。返信のあった質問用紙は、内容をまとめ、内容をカテゴリー化していく。
手順:研究の説明書、研究への参加依頼書、緩和ケア師長への質問用紙、インタビュー 参加同意書を日本全国の緩和ケア病棟に送付する。師長にコンタクトパーソンとなってもらい、師長への質問用紙とインタビュー参加同意書を研究者へ返信してもらう。インタビュー参加に同意してくれたナースに連絡を取り、インタビューの日程、時間、場所を決める。
|
 |
III 実施経過 実施経過 |
 本研究は三年計画の一年目にあたる。前半、10月までの期間に、本研究のトピックに関連する国際文献約200部を収集し(日本に関する文献約40部を含む)、幅広く文献レビューを行った。2005年11月~2006年2月にかけて、研究の計画書、研究方法について研究指導者との検討を重ねている。現在、モナシュ大学看護学科緩和ケアのMargaret O'Connor教授と研究の専門Ken Sellick博士の指示を仰いでいる。また、医療者の悲嘆の研究を世界的で先駆的に行っている、ギリシャのPapadatou教授に連絡をとり、医療者の悲嘆について直接指示を仰いでいる。Papadatou教授は、小児がん医療にあたるナースと医師の悲嘆について、また、ギリシャと香港における医療者の悲嘆の比較研究などを実施している(Papadatou, 2000; Papadatou, 2001; Papadatou et al., 2001; Papadatou et al., 2002)。さらに、研究の一環として悲嘆や医療者が現場で経験するストレスについての専門家であるロビン・ロビンソン博士とマル・マッキソック博士に「医療者、特にナースが経験する悲嘆」についてアドバイスをいただいている。 本研究は三年計画の一年目にあたる。前半、10月までの期間に、本研究のトピックに関連する国際文献約200部を収集し(日本に関する文献約40部を含む)、幅広く文献レビューを行った。2005年11月~2006年2月にかけて、研究の計画書、研究方法について研究指導者との検討を重ねている。現在、モナシュ大学看護学科緩和ケアのMargaret O'Connor教授と研究の専門Ken Sellick博士の指示を仰いでいる。また、医療者の悲嘆の研究を世界的で先駆的に行っている、ギリシャのPapadatou教授に連絡をとり、医療者の悲嘆について直接指示を仰いでいる。Papadatou教授は、小児がん医療にあたるナースと医師の悲嘆について、また、ギリシャと香港における医療者の悲嘆の比較研究などを実施している(Papadatou, 2000; Papadatou, 2001; Papadatou et al., 2001; Papadatou et al., 2002)。さらに、研究の一環として悲嘆や医療者が現場で経験するストレスについての専門家であるロビン・ロビンソン博士とマル・マッキソック博士に「医療者、特にナースが経験する悲嘆」についてアドバイスをいただいている。 |
 |
IV 調査・研究の成果 調査・研究の成果 |
 本年度は文献レビューとプロフェッショナルアドバイスを研究プロセスとして計画していた。研究の成果として、文献レビューとプロフェッショナルアドバイスについて報告する。 本年度は文献レビューとプロフェッショナルアドバイスを研究プロセスとして計画していた。研究の成果として、文献レビューとプロフェッショナルアドバイスについて報告する。
文献レビュー
医療者の悲嘆に関する研究:国外および国内における研究状況;
 医療者の悲嘆に関する研究は、国内外でその不足が指摘されている。多数の文献を検索する中で、国外において医療者の悲嘆を専門としている研究者が何名かいることが明らかになった。ただし、そのほとんどが小児医療において死を見取る医療者の悲嘆に焦点があてられており(Davies et al., 1996; Hinds et al., 1994; Papadatou et al., 2001; Papadatou et al., 2002; Talma, Stanley & Sima, 1997)、緩和ケア分野での医療者の悲嘆に関する研究は非常に少ない(Redinbaugh et al., 2001)。 医療者の悲嘆に関する研究は、国内外でその不足が指摘されている。多数の文献を検索する中で、国外において医療者の悲嘆を専門としている研究者が何名かいることが明らかになった。ただし、そのほとんどが小児医療において死を見取る医療者の悲嘆に焦点があてられており(Davies et al., 1996; Hinds et al., 1994; Papadatou et al., 2001; Papadatou et al., 2002; Talma, Stanley & Sima, 1997)、緩和ケア分野での医療者の悲嘆に関する研究は非常に少ない(Redinbaugh et al., 2001)。
 特に緩和ケアを専門とする医療者は、終末期の患者の苦痛・苦悩そして死、さらに家族の悲嘆やそれに関連するさまざまな感情を目撃する。他者の苦しみや悲嘆の目撃者となるという経験を通して、医療者自身が悲嘆を感じたり、過去に経験している悲嘆が呼び起こされる可能性があるといわれている。Papadatouは彼女の研究の中で、医療者は悲嘆を表現することと、表現することを避けることの狭間で揺れていると述べている。そして、医療者が自らの悲嘆を表現することを避け続けるならば、または否定し続けるならば、悲嘆の蓄積がおこりバーンアウトにつながるといわれる(Papadatou et al., 2002; Vachon, 1995)。 特に緩和ケアを専門とする医療者は、終末期の患者の苦痛・苦悩そして死、さらに家族の悲嘆やそれに関連するさまざまな感情を目撃する。他者の苦しみや悲嘆の目撃者となるという経験を通して、医療者自身が悲嘆を感じたり、過去に経験している悲嘆が呼び起こされる可能性があるといわれている。Papadatouは彼女の研究の中で、医療者は悲嘆を表現することと、表現することを避けることの狭間で揺れていると述べている。そして、医療者が自らの悲嘆を表現することを避け続けるならば、または否定し続けるならば、悲嘆の蓄積がおこりバーンアウトにつながるといわれる(Papadatou et al., 2002; Vachon, 1995)。
 さらに医療者の経験する悲嘆の特徴として、社会に認められない悲嘆(患者・医療者の関係が、その死を悲しむ喪失として社会に認められていない)、そして予期悲嘆があげられている(Doka, 2002; Renzenbrink, 2005; Wakefield, 2000)。また、患者の死を通して、医療者としての自信を失ったり、自分の家族と重ねて悲しんだり、医療者自身の過去の喪失を再び悲しんだり、自分の死を考えたりという特徴が報告されている(Papadatou, 2000)。さらにFigley(1995)は、医療者がCompassion Fatigue(コンパッション疲労)を経験しやすいと述べている。Compassion Fatigueとは、難しい経験をしている他者・苦悩の中にいる他者を援助していること、または援助したいという思いからくるストレス、他者が経験している難しい経験(トラウマとなるような経験)について知ることによっておこる行動的・感情的な反応である(Figley, 1995)。さらに注目すべきことは、ナースが最もこのCompassion Fatigueを経験しやすいという報告である。 さらに医療者の経験する悲嘆の特徴として、社会に認められない悲嘆(患者・医療者の関係が、その死を悲しむ喪失として社会に認められていない)、そして予期悲嘆があげられている(Doka, 2002; Renzenbrink, 2005; Wakefield, 2000)。また、患者の死を通して、医療者としての自信を失ったり、自分の家族と重ねて悲しんだり、医療者自身の過去の喪失を再び悲しんだり、自分の死を考えたりという特徴が報告されている(Papadatou, 2000)。さらにFigley(1995)は、医療者がCompassion Fatigue(コンパッション疲労)を経験しやすいと述べている。Compassion Fatigueとは、難しい経験をしている他者・苦悩の中にいる他者を援助していること、または援助したいという思いからくるストレス、他者が経験している難しい経験(トラウマとなるような経験)について知ることによっておこる行動的・感情的な反応である(Figley, 1995)。さらに注目すべきことは、ナースが最もこのCompassion Fatigueを経験しやすいという報告である。
 専門性を通して悲嘆やCompassion Fatigueを経験する可能性が高い医療者に対して、大きく分けて3つのサポートが提唱されている。まずは組織からのサポート、そして病棟レベルでのサポート、最後にセルフケアである。組織からのサポートとは、医療者の属する組織が、医療者のサポートニーズについて理解を示すこと、そして病棟レベルでのスタッフケアをサポートすること、そして教育を提供することと言われている(Keidel, 2002; Marino, 1998; Renzenbrink, 2005)。病棟レベルでのサポートは、Debriefing session(振り返りセッション)、同僚間のサポート、スーパービジョン、教育などが含まれてくる(Kaplan, 2000; Yassen, 1995)。同じような経験をしている同僚同士がその経験や感情を共有できること、そしてスーパービジョンなどを通して適切なケアとアドバイスが受けられることが重要視されている。最後に医療者自身のサポートとして、セルフケアの重要性がいわれている。他者のケアに携わる専門家として、医療者がセルフケアを行うことはケアを提供する専門職として大切な責任の一つである。このセルフケアには自らをケアすることと同時に、自らを知ること(自己認知)が含まれている。自己認知とは、なぜ自分がこの専門を選んだのか、モチベーションはどこにあるか、自分の痛みは何か、その痛みはどんな段階か、そして必要ならばどこに助けを求めるかなどを知ることである(Kaplan, 2000; Sherman, 2004)。 専門性を通して悲嘆やCompassion Fatigueを経験する可能性が高い医療者に対して、大きく分けて3つのサポートが提唱されている。まずは組織からのサポート、そして病棟レベルでのサポート、最後にセルフケアである。組織からのサポートとは、医療者の属する組織が、医療者のサポートニーズについて理解を示すこと、そして病棟レベルでのスタッフケアをサポートすること、そして教育を提供することと言われている(Keidel, 2002; Marino, 1998; Renzenbrink, 2005)。病棟レベルでのサポートは、Debriefing session(振り返りセッション)、同僚間のサポート、スーパービジョン、教育などが含まれてくる(Kaplan, 2000; Yassen, 1995)。同じような経験をしている同僚同士がその経験や感情を共有できること、そしてスーパービジョンなどを通して適切なケアとアドバイスが受けられることが重要視されている。最後に医療者自身のサポートとして、セルフケアの重要性がいわれている。他者のケアに携わる専門家として、医療者がセルフケアを行うことはケアを提供する専門職として大切な責任の一つである。このセルフケアには自らをケアすることと同時に、自らを知ること(自己認知)が含まれている。自己認知とは、なぜ自分がこの専門を選んだのか、モチベーションはどこにあるか、自分の痛みは何か、その痛みはどんな段階か、そして必要ならばどこに助けを求めるかなどを知ることである(Kaplan, 2000; Sherman, 2004)。
 日本の医療・緩和ケア、そしてグリーフケアの現状を考えたときに、文化的独自性がみえてくる。まずは、緩和ケアが入院施設中心であること。そして、オーストラリアと比較して緩和ケア平均入院日数が長いこと(2004年、日本46.29日に対し、オーストラリア10~12日)。そして、全人的アプローチを目指す緩和ケアでナースの果たす役割がとても大きいということ。このような中、ナースたちはより長く患者・家族をケアし、その中で深い関係を築き、時に患者や家族から強い感情表現を受け、患者と家族の悲嘆の目撃者となり、そして患者を看取っている。さらに現代社会において核家族化がすすみ、社会的背景の変化も伴って、親族を含む家族の中でおこなわれていたグリーフケアが、医療の役割へと徐々に変化してきている(Matsushima et al., 2002)。日本の研究者によって発表された研究では、遺族のグリーフケアの現状に焦点があたっている。その中で、グリーフケアの充実とグリーフケアにあたる医療者の教育の必要性が述べられている。日本の遺族へのグリーフケアの特徴的な点は、グリーフケア提供者で最も多いのがグリーフケア専門の医療者やカウンセラーなどではなく、現場で亡くなりゆく患者をケアしているナースであるということである(Matsushima et al., 2002; Sakaguchi et al., 2004)。 日本の医療・緩和ケア、そしてグリーフケアの現状を考えたときに、文化的独自性がみえてくる。まずは、緩和ケアが入院施設中心であること。そして、オーストラリアと比較して緩和ケア平均入院日数が長いこと(2004年、日本46.29日に対し、オーストラリア10~12日)。そして、全人的アプローチを目指す緩和ケアでナースの果たす役割がとても大きいということ。このような中、ナースたちはより長く患者・家族をケアし、その中で深い関係を築き、時に患者や家族から強い感情表現を受け、患者と家族の悲嘆の目撃者となり、そして患者を看取っている。さらに現代社会において核家族化がすすみ、社会的背景の変化も伴って、親族を含む家族の中でおこなわれていたグリーフケアが、医療の役割へと徐々に変化してきている(Matsushima et al., 2002)。日本の研究者によって発表された研究では、遺族のグリーフケアの現状に焦点があたっている。その中で、グリーフケアの充実とグリーフケアにあたる医療者の教育の必要性が述べられている。日本の遺族へのグリーフケアの特徴的な点は、グリーフケア提供者で最も多いのがグリーフケア専門の医療者やカウンセラーなどではなく、現場で亡くなりゆく患者をケアしているナースであるということである(Matsushima et al., 2002; Sakaguchi et al., 2004)。
 これらの背景から、また冒頭に述べた日本の医療者の声から、日本においてナースが職場で経験している悲嘆について理解を深め、サポートシステムを確立することは不可欠であると言えよう。 これらの背景から、また冒頭に述べた日本の医療者の声から、日本においてナースが職場で経験している悲嘆について理解を深め、サポートシステムを確立することは不可欠であると言えよう。
プロフェッショナルアドバイス
本研究の一環として、下記のスペシャリスト方のアドバイスを受ける機会を得た。それぞれの先生方は、数少ない「医療者の悲嘆」という分野での研究の重要性にとても共感され、自身の経験と知識を用いて下記のようなアドバイスをされた。
Dr. Robyn Robinson(ロビン・ロビンソン博士)
 心理学者であり、Clinical Incident Stress Management Association in Australiaの会長 心理学者であり、Clinical Incident Stress Management Association in Australiaの会長
 医療者の悲嘆とストレス・バーンアウトの関係について; 医療者の悲嘆とストレス・バーンアウトの関係について;
 医療者が経験する悲嘆やトラウマは、一般的に理解されているストレス・バーンアウトとは性格を異にする。医療者が経験する悲嘆やトラウマは、医療者にさまざまな側面から影響を及ぼし、個人の内面に触れ、過去の経験を再び呼び起こすことになる。 医療者が経験する悲嘆やトラウマは、一般的に理解されているストレス・バーンアウトとは性格を異にする。医療者が経験する悲嘆やトラウマは、医療者にさまざまな側面から影響を及ぼし、個人の内面に触れ、過去の経験を再び呼び起こすことになる。
 さらに、ストレスとクリティカル・インシデント・ストレスと悲嘆の関連について、下記のようなモデルを示された。ストレスは結果としてバーンアウトやストレスの蓄積をもたらす。クリニカル・インシデント・ストレスは、その結果としてPost Traumatic Stress Disorderを引き起こす可能性が高い。医療者の悲嘆は、その結果として複雑な悲嘆をもたらす可能性がある。これを防ぐには、予防的に、そして継続的にサポートを提供することである。 さらに、ストレスとクリティカル・インシデント・ストレスと悲嘆の関連について、下記のようなモデルを示された。ストレスは結果としてバーンアウトやストレスの蓄積をもたらす。クリニカル・インシデント・ストレスは、その結果としてPost Traumatic Stress Disorderを引き起こす可能性が高い。医療者の悲嘆は、その結果として複雑な悲嘆をもたらす可能性がある。これを防ぐには、予防的に、そして継続的にサポートを提供することである。
(下図参照)
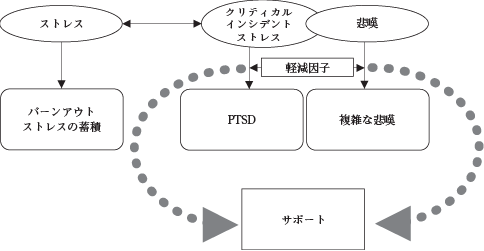
医療者の悲嘆に対する研究の可能性について;
 世界的に見ても、医療者の悲嘆は今まであまり焦点が当たってこなかった分野である。まずは、ナースたちの経験を「語ってもらう」ことから始めなければならない。このような内容を「語る」という経験は、今後ナースたちのPeer Support (同僚間のサポート)につながっていくだろう。この際に考慮しなければならないのは、「語る」ということに関して、ナースのスピリチュアリティーや文化的背景がどのように影響するかという点であろう。また将来的に、異なる文化において、医療者が経験する悲嘆やその表現に違いがあるか国際間の比較研究も意味があるであろう。また、先に述べたようにこの分野の研究は世界的にみても少ないのが現状である。日本のナースを対象におこなわれる研究であるが、この研究の結果は日本以外の医療者にとっても重要な内容になるであろう。 世界的に見ても、医療者の悲嘆は今まであまり焦点が当たってこなかった分野である。まずは、ナースたちの経験を「語ってもらう」ことから始めなければならない。このような内容を「語る」という経験は、今後ナースたちのPeer Support (同僚間のサポート)につながっていくだろう。この際に考慮しなければならないのは、「語る」ということに関して、ナースのスピリチュアリティーや文化的背景がどのように影響するかという点であろう。また将来的に、異なる文化において、医療者が経験する悲嘆やその表現に違いがあるか国際間の比較研究も意味があるであろう。また、先に述べたようにこの分野の研究は世界的にみても少ないのが現状である。日本のナースを対象におこなわれる研究であるが、この研究の結果は日本以外の医療者にとっても重要な内容になるであろう。
Mr. Mal McKissock(マル・マッキソック先生)
 オーストラリアのグリーフケア提供と教育の第一人者である。オーストラリア全土、ニュージーランド、香港において、グリーフケアに携わる人々を対象としてグリーフケアの教育を提供している。また、専門のカウンセラーたちのスーパーバイザーとして、グリーフカウンセリングを指導している。また、シドニーにBereavement C.A.R.E. centreを設立し、悲嘆を経験している子供のグリーフケアを定期的におこなっている。 さらにMal先生自身ナースであり、ホスピス100床の病院の看護部長をしていた経験から、このようなアドバイスがあった。 オーストラリアのグリーフケア提供と教育の第一人者である。オーストラリア全土、ニュージーランド、香港において、グリーフケアに携わる人々を対象としてグリーフケアの教育を提供している。また、専門のカウンセラーたちのスーパーバイザーとして、グリーフカウンセリングを指導している。また、シドニーにBereavement C.A.R.E. centreを設立し、悲嘆を経験している子供のグリーフケアを定期的におこなっている。 さらにMal先生自身ナースであり、ホスピス100床の病院の看護部長をしていた経験から、このようなアドバイスがあった。
 ナースの悲嘆に対するサポートは不可欠だが、そのためには病院という組織文化の意識改革が必要である。悲嘆は重要な関係の喪失といわれるが、ナースは患者・家族と特別な関係を築いており、患者の死によってそれを失うことになる。特に、多くの死を看取る緩和ケアナースは特殊な位置にいると考えなければならない。さらに、ナースは援助することを目的としている専門職であり、患者の死によって無力感や罪責感を強く感じることがしばしばある。強い無力感や罪責感などの感情は、悲嘆の経験を複雑にする可能性が非常に高い。 ナースの悲嘆に対するサポートは不可欠だが、そのためには病院という組織文化の意識改革が必要である。悲嘆は重要な関係の喪失といわれるが、ナースは患者・家族と特別な関係を築いており、患者の死によってそれを失うことになる。特に、多くの死を看取る緩和ケアナースは特殊な位置にいると考えなければならない。さらに、ナースは援助することを目的としている専門職であり、患者の死によって無力感や罪責感を強く感じることがしばしばある。強い無力感や罪責感などの感情は、悲嘆の経験を複雑にする可能性が非常に高い。
ナースへのインタビューについて;
 仕事上経験する悲嘆について焦点を当てるときに、そのナースの仕事の部分にだけ焦点を当てるのは十分ではない。なぜならば、ナースになった動機、過去の喪失・悲嘆の経験、普段持っている社会的サポート、家族環境などが、悲嘆の経験に多大にかかわってくるからである。これらの要素を含んだ質問事項を作成後、インタビューをする研究者自身が、そのインタビューに答えてみるという経験をするとよい。個人的な悲嘆という経験を語るということについて、インタビューするもの自身が十分な理解をしておく必要がある。 仕事上経験する悲嘆について焦点を当てるときに、そのナースの仕事の部分にだけ焦点を当てるのは十分ではない。なぜならば、ナースになった動機、過去の喪失・悲嘆の経験、普段持っている社会的サポート、家族環境などが、悲嘆の経験に多大にかかわってくるからである。これらの要素を含んだ質問事項を作成後、インタビューをする研究者自身が、そのインタビューに答えてみるという経験をするとよい。個人的な悲嘆という経験を語るということについて、インタビューするもの自身が十分な理解をしておく必要がある。
 Papadatou教授リサーチ結果に基づいた医療者の悲嘆に関するインタビューの可能性について; Papadatou教授リサーチ結果に基づいた医療者の悲嘆に関するインタビューの可能性について;
 ギリシャ語原文で送られる質問事項を英文に翻訳し、それが日本の背景に沿うか吟味する必要がある。ナースの悲嘆による影響を捕らえるために、GHQ(General Health Questionnaire)などを併用する必要があるかもしれない。 ギリシャ語原文で送られる質問事項を英文に翻訳し、それが日本の背景に沿うか吟味する必要がある。ナースの悲嘆による影響を捕らえるために、GHQ(General Health Questionnaire)などを併用する必要があるかもしれない。
 この研究の意義; この研究の意義;
 この研究の意義はとても大きい。世界的に見てもこの分野での研究はまだ十分ではない。多くのナースが自らの悲嘆に気づいており、組織もそれに気づいている。ただ、それに対する理解やサポートは十分とはいえない。この研究の結果によって、日本の医療現場のみならず、日本以外の医療者たちが多くを学ぶであろう。 この研究の意義はとても大きい。世界的に見てもこの分野での研究はまだ十分ではない。多くのナースが自らの悲嘆に気づいており、組織もそれに気づいている。ただ、それに対する理解やサポートは十分とはいえない。この研究の結果によって、日本の医療現場のみならず、日本以外の医療者たちが多くを学ぶであろう。
 上記2名のプロフェッショナルアドバイスに基づいて、本研究では下記の点を指針として得た。 上記2名のプロフェッショナルアドバイスに基づいて、本研究では下記の点を指針として得た。
☆ナースの悲嘆について、十分な研究がなされてこなかった。研究の意義は大きい。
☆「語る」ということを中心としたインタビュー形式での研究
☆日本という文化・社会・医療体制などに対する考慮
☆「個人の悲嘆」というとてもセンシティブな内容にふれるインタビューになるため、インタビューをおこなう研究者がそのような経験を語るということを十分に配慮する必要がある。 |
 |
V 今後の方向 今後の方向 |
 2006年度は本研究の2年目にあたる。 2006年度は本研究の2年目にあたる。
 研究方法を決定後、研究計画全体に対しモナシュ大学倫理委員会の審査を受け、本年7月以降に日本においてデータ収集(インタビューと質問用紙)を開始する計画である。インタビュー内容がナースの個人的体験、悲嘆の経験に焦点をあてるため、個人の内面に触れる可能性が強く、十分な倫理的配慮が求められる。 研究方法を決定後、研究計画全体に対しモナシュ大学倫理委員会の審査を受け、本年7月以降に日本においてデータ収集(インタビューと質問用紙)を開始する計画である。インタビュー内容がナースの個人的体験、悲嘆の経験に焦点をあてるため、個人の内面に触れる可能性が強く、十分な倫理的配慮が求められる。 |
 |
VI 調査・研究の成果等公表予定 調査・研究の成果等公表予定 |
 「医療者の悲嘆に関する研究:国外および国内における研究状況」の内容について、日本、または海外の看護系雑誌への投稿を検討している。 「医療者の悲嘆に関する研究:国外および国内における研究状況」の内容について、日本、または海外の看護系雑誌への投稿を検討している。 |
 |
| 本要約における参考文献 |
Davies, B., Cook, K., O'Loane, M., Clarke, D., MacKenzie, B., Stutzer, C. (1996). Caring for dying children: Nurses' experiences. Pediatric Nursing, 22(6), 507.
Doka, K. J. (2002). Disenfranchised grief: New directiions, challenges, and strategies for practice. Illinois, USA: Research Press.
Figley, C. R. (1995). Compassion Fatigue: Copint with Secondary Traumatic Stress Disorder in Those Who Trest the traumatized. New York: Brunner-Routledge.
Hinds, P. S., Puckett, P., Donohoe, M., Milligan, M., Payne, K., Phipps, S. (1994). The impact of a grief workshop for pediatric oncology nurses on their grief and perceived stress. 9, 6, 388-397.
Kaplan, L. J. (2000). Toward a model of caregiver grief: Nurses' experiences of treating dying children. Omega, 41(3), 187-206.
Keidel, G. C. (2002). Burnout and compassion fatigue among hospice caregivers. American Journal of Hospice & Palliative Care, 19(3), 200-205.
Marino, P. A. (1998). The effects of cumulative grief in the nurse. Journal of IV Nursing, 21(2), 101-104.
Matsushima, T., Akabayashi, A., & Nishitateno, K. (2002). The current status of bereavement follow-up in hospice and palliative care in japan. Palliative Medicine, 16, 151-158.
Papadatou, D. (2000). A Proposed Model of Health Professional's Grieving Process. Omega, 41 (4), 59-77.
Papadatou, D. (2001). The grieving healthcare provider: Vriables affecting the professional response to a child's death. Bereavement Care, 20 (2), 26-29.
Papadatou, D., Martinson, I. M., & Chung, P. M. (2001). Caring for dying children: A comparative study of nurses' experieces in greece and hong kong. Cancer Nursing - An International Journal for Cancer Care, 24(5), 402-412.
Papadatou, D., Papazoglou, I., Bellali, T., & Petraki, D. (2002). Greek nurse and physician grief as a result of caring for children dying of cancer. Pediatric Nursing, 28(4), 345-353.
Redinbaugh, E. M., Schuerger, J. M., Weiss, L. L., Brufsky, A., & Arnold, R. (2001). Health care professionals' grief: A model based on occupational style and coping. Psycho-Oncology, 10, 187-198.
Renzenbrink, I. (2005). Staff support: Whose responsibility? Grief Matters, 13-17.
Sakaguchi, Y., Tsuneto, S., Takayama, K., Tamura, K., Ikenaga, M., & Kashiwagi, T. (2004). Global exchange: Tasks perceived as necessary for hospice and palliative care unit bereavement services in Japan. Journal of Palliative Care, 20(4), 320-323.
Sherman, D. W. (2004). Nurses' stress & burnout. AJN, 104(5), 48-56.
Talma, K., Stanley, R., & Sima, A. (1997). A descriptive study of stress management in a group of pediatric oncology nurses. Cancer Nursing - An International Journal for Cancer Care, 20(6), 414-421.
Vachon, M. L. S. (1995). Staff stress in hospice/palliative care: A review. Palliative Medicine, 9, 91-122.
Wakefield, A. (2000). Nurses' responses to death and dying: A need for relentless self-care. International Journal of Palliative Nursing, 6-5, 245-251.
Yassen, J. (1995). Preventing Secondary Traumatic Stress Disorder. In C. R. Figley (Ed), Compassion Fatigue: Coping with Secondary Traumatic Stress Disorder in Those Who Treat the Traumatized (pp. 178-208). New York: Brunner-Routledge. |
|

